9. カーエレクトロニクスへの着手
1949-
(2)IC生産への挑戦
- 1967年
- 将来の電装品のエレクトロニクス化が予見されるようになった。当社は入念な調査の上で、まだ困難とされていたIC(集積回路)の自社開発、さらにその自社生産に挑戦すると決断した。

日本の半導体研究は、1950年ごろから米国の後追いで始められた。1956年には民生用トランジスターの国内生産が可能となるまでになっていた。
エレクトロニクス技術の電装品への応用については、当社も早くから関心を抱いていた。
1962年には、シリコンダイオードを利用した「レクチファイア付きオルタネーター」を国内で初めて製品化した。しかし、使用環境が格段に厳しい自動車用電装品には、家電用素子では適応に無理があった。その仕様の決定にも、自動車の市場環境を踏まえたノウハウが必要であった。
当社が購入するレクチファイアもトラブルが多発しており、当社の生産にも支障を来していた。しかしながら、当社には半導体の製造経験がないため、問題解決の能力がなかった。そればかりか、メーカーへ改善策を伝えることも満足にできなかった。
当時、市場で出回り始めたIC(集積回路)を自社生産できるよう、早急に体制を構築することが必要であった。しかし、半導体事業には巨額の設備投資負担とリスクが伴う。これに安易に着手することはできなかった。それでも当社は、困難といわれるIC事業について、入念な調査と検討を重ねた。
満を持して1967年3月、岩月達夫社長は「IC製造を含むエレクトロニクス事業」を開始することを決断した。手始めに、社内にIC研究の準備プロジェクトを発足させた。
- 深掘り岩月社長の思い
- 「電装もエレクトロニクスを始めた」と聞いた岩月社長が、北工場の製造現場を見てきて、生産技術担当の取締役に言った。「他社から買ってきた部品をプリント板の穴に刺してハンダづけをしていることのどこがエレクトロニクスか。俺は情けない。あの差し込んでいるトランジスターやICを作るのがエレクトロニクスではないか」
言われた取締役は、「それなら社長のあなたがICを作れと命令されたら、私はやりますよ」と答えた。
岩月社長は、「俺はICをやりたい。お前が担当せよ」と命じた。ここから日本電装のIC事業への挑戦が始まったと言われている。
当社のIC事業への挑戦は、研究だけでなく、最初から自社生産を視野に入れていた。これが大きな特徴であった。研究開発と並行して、製造設備の調査にも取り掛かった。結果としては、これがその後の事業の成功に至った大きな要因といわれることになった。
- 深掘りIC自社生産の考え方
- ICは研究だけ続ければ優位が崩れないという人もいたが、当時の当社のリーダーは、「ICを他社で作ってもらうためには、当社が汗と金を注ぎ込んで積み上げてきた自動車部品のノウハウを洗いざらい教えなければならない。これでは当社は他社のために苦労した揚げ句、社業の衰退を招く」と考えた。
ICの自社生産については、関連する役員が自らさまざまな調査を続けていた。国内外の展示会の見学、社外の予備調査、関係先との折衝などを重ねた。その上で、「IC製造工程は化学処理中心の長大なものであり、設備の種類や台数も多く複雑であるが、当社でのIC製造は可能」という考えが次第にまとまっていった。
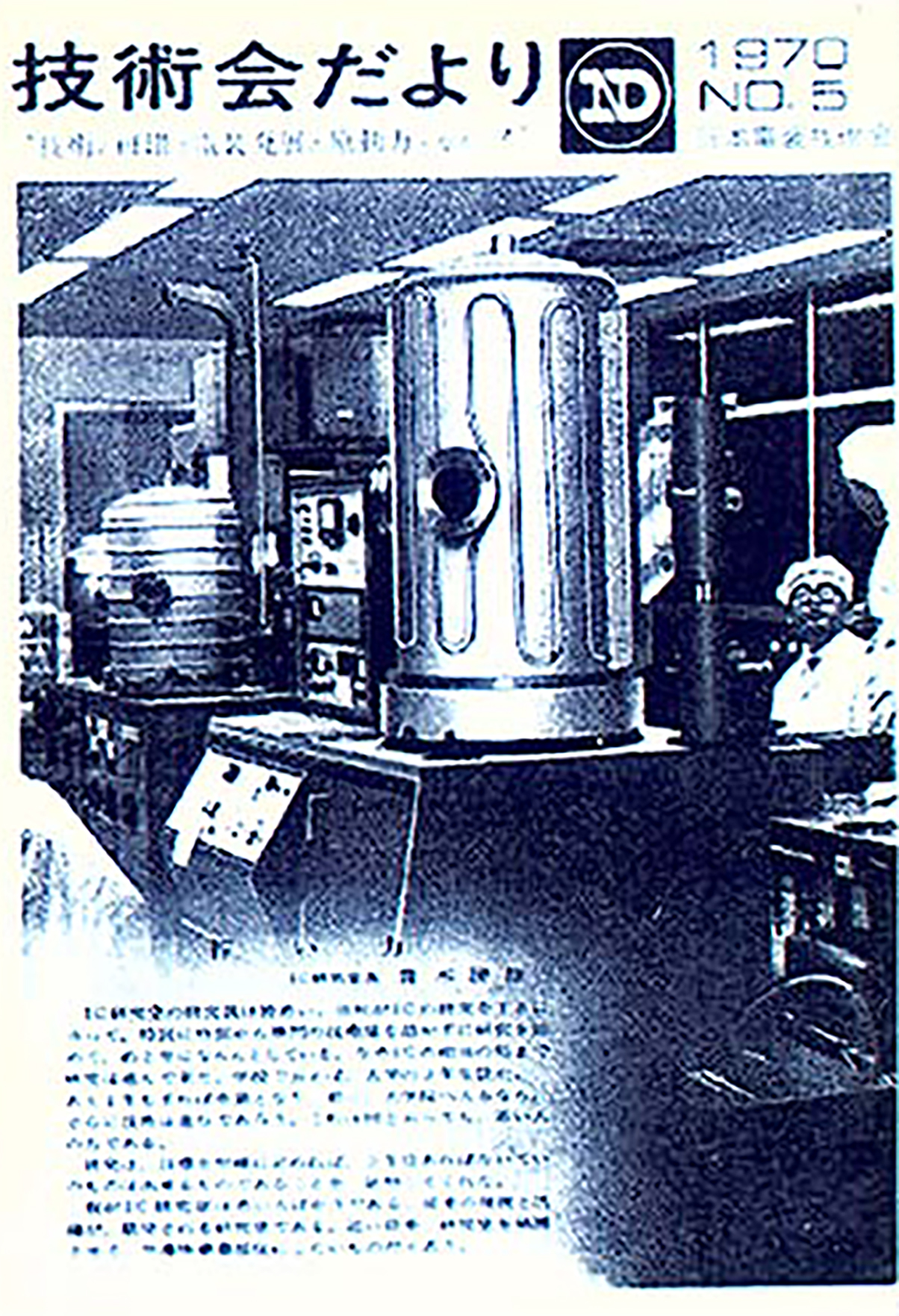
次の段階として、専用の研究室の建設を検討した。半導体素子の製造研究とその自動車部品への応用研究に本格的に取り組むためであった。
技術先進国の米国におけるクリーンルームのレベルなども実地調査した上で、1968年10月、本社内に「IC研究棟」を建設した。これは、その後長らく「IC研究室」と呼ばれ、当社のIC研究活動の本山となった。
IC製造については、1969年に米国のテキサス・インスツルメント社などと半導体の基本特許契約を交わし、「IC製造の許諾」を得ることができた。
残る問題は、「人」であった。当時、中部地方は“半導体産業不毛の地“といわれ、ここで戦力となるIC技術者を採用することは不可能であった。やむなく当社は、新入社員を中核とした素人集団での勉強会からスタートせざるをえなかった。
その後、研究の格段の進展を図るため、理論面と実務面の先生をつけることとした。東芝と米国RCA社から指導を受けることができた。
こうした努力を地道に続けた結果、当社のIC技術は次第に独り立ちできるレベルに到達していった。1970年代後半には、当社独自で何とか事業体を構築できるまでにもっていくことができた。