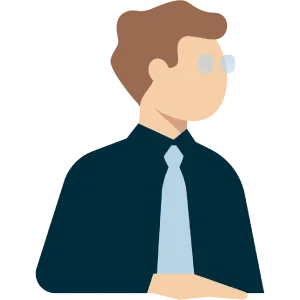あなたが実現したいこと、学びたいこと、可能性を広げたいことに、この記事は役に立ちましたか?
ぜひ感じたことを編集部とシェアしてください。
-
菊池 伸一Shinichi Kikuchi
大学院工学研究科を修了後、複数の会社でBtoCやBtoBなどのシステム開発に携わり、2020年にデンソー入社。先端技能開発部で技能者として自動運転関連のソフトウェア開発を進め、研究開発を行う技術員をサポート。現在はバッテリーパスポートの主要開発者として活躍し、4チームをリーダーとして束ねている。
QRコード®とブロックチェーンの技術を活用し、バッテリーのライフサイクル全体の情報を記録するデジタル証明書「バッテリーパスポート」の開発を進めているデンソー。その主要開発者として活躍するのが、先端技能開発部 モビリティ実験室の菊池 伸一です。大切にしている「コトづくり」の価値観や、思い描く未来について語ります。
この記事の目次
QRコード×ブロックチェーンで「バッテリーパスポート」を開発

──今日はよろしくお願いします。まずは現在の仕事内容から教えていただけますか?
技術員が研究開発している新技術に対し、技能者として具現化や試作、価値実証を行っています。具体的には、ブロックチェーンのPoC(概念実証)のためのシステム開発や基盤開発です。また、デンソーが開発したトレーサビリティ技術である「QR in QR(2種類のQRコードの情報を1つにまとめる技術)」について、読み取りの高速化も進めています。
最近ではQRコードとブロックチェーンの技術を活かし、バッテリーパスポートの開発にも力を注いでいます。2027年からEU域内で流通するすべてのEV用バッテリーにバッテリーパスポートが義務化されるため、施行前のリリースをめざして要件定義や設計を行っているところです。
営業担当者がお客さまから伺ったご要望をもとに、要件定義をする技術員のチームと、私が所属する技術員と技能員の開発チームが連携し、「お客さまにとって本当に価値のあるものは何か」を定義しています。
──その一方で、以前は自動運転関連の仕事もしていたそうですね。
はい。入社後しばらくは技能者として、技術員の自動運転の研究開発をサポートする実験車用のソフトウェア開発を担当していました。そこからチームが拡大し、現在では実験車両による評価だけでなく仮想空間でデータを収集するなど、技術員が自動運転研究を加速できるよう支援しています。
──現在、技術員と連携する中で心がけていることはありますか?
連日顔を合わせて信頼関係を深め、作業のスピードと精度を高めるよう努めています。今取り組んでいるのはクラウド上でソフトウェアをサービスとして利用できるITの仕組み(SaaS:Software as a Service)であり、デンソーでも事例が少ない中で新しい価値を生み出すことが求められています。
そういう意味で、私たちのチームは一つのIT企業のような存在かもしれません。これまでモノづくりに励んできたデンソーで、今後はコトづくりを推進したいと考えています。大変ではありますが、やる気と楽しさに満ちています。
1人より、チームで協力したほうがもっと遠くまで行ける

──これまでのプロセスも聞かせてください。学生時代はどのように過ごしていましたか?
高校時代、ITバブルの中で情報システムに関心を持つようになりました。プログラミングに取り組むと夢中になり、のめり込みましたね。システムは論理的に考えれば作れるため、ゲームのように楽しく感じました。大学院でシステム開発を重ねるうちに自分に合っていると確信し、その分野で就職しました。
──その後、社会人としてキャリアを築く中でデンソーに転職したのはなぜですか?
複数の会社でBtoC、BtoB、社内システム開発と既存システムの改修に多く携わるうちに「世に出ていないまったく新しい技術に触れて新しいモノやコトを生み出したい」という思いが膨らみました。当時はマネジメント中心になっていて、「自分の手を動かしたい」とも考えていました。
そんな中で出会ったのがデンソーです。社員の記事を読む中でソフトウェアに力を入れ始めたことを知り、自動運転にも関われそうだと感じて入社を決めました。
──実際に働いてみて、いかがですか?
思い描いていた通りの仕事ができ、充実感を得ています。研究開発は5年、10年かけても成果が結実しないことも多いですが、バッテリーパスポートはすでに世に出せる段階にあります。
企画から実装まで一気通貫で進められるからこそ、このスピード感が出せるのだと思います。上司が「デンソーは自分たちでなんでも作ってしまう」と話していて、会社としての規模の大きさ、懐の深さを実感しています。
──現在マネジメントも担う中で、どんなことに気を配っていますか?
毎朝のミーティングで困りごとや方針を話し合うほか、事前に計画を立て情報を共有しながら業務を進める「段取りコミュニケーション」を大切にしています。1人よりチームで協力した方が、より遠くまで行ける、つまり成果と成長を最大化できるからです。全員で協力する雰囲気をつくり、誰も置いていかれないようにしています。
最近では私が不在でもメンバーが自主的にミーティングを開いており、チームのまとまりが増してきて、とても頼もしいです。
デンソーには、世にまだない技術の種がたくさん転がっている

──デンソーで働く中で、とくに印象に残っている出来事はありますか?
2つあります。まずは2020年、入社して自動運転に関わっていた頃です。前職では社内用システムの開発を担当していたため、世の中の安心・安全に直結する自動運転の開発に携われることに大きなやりがいを感じました。
ただ初めての分野でわからないことが多く、即戦力にはなりませんでしたが、夢中で技術に触れノウハウを身につける時間をいただけたことが、何よりありがたく心に残っています。
──もう一つの印象深い出来事とは何ですか?
ソフトウェア開発者が増え、私が班長になった時です。メンバーの得意・不得意を把握し、どう成長につなげるかを考える必要があり、マネジメントに苦労しました。
周囲のマネージャーを観察したり、書籍で学んだりしましたが、簡単にはできませんでした。それでも焦らず丁寧に向き合うことで、次第にメンバーが成果を出すようになってきました。時間はかかりましたが、何よりもうれしいことでした。
──やりがいを感じるのはどんな時ですか?
デンソーには世にまだない技術の種が数多くあり、そこから価値創出に挑戦できるのが大きなやりがいです。調べても答えが見つからないと「もしかして世界初かもしれない」とワクワクします。
しかもチームでチャレンジできるのが楽しいですね。1人では生み出せるアイデアに限界がありますが、メンバーがそれぞれの視点で試し、共有し合うことで可能性が広がり、新たな技術や価値につながります。「チームのために全力をつくしたい」というデンソースピリットを日々実感しています。
また、技術を活用して社会課題の解決をめざせることもあり、自分の視野が一気に広がりました。これからは全世界のユーザーの視点も意識して進めていきたいです。
他の領域も広く見据え、汎用的な開発で未来を描く

──現在携わっている仕事について、どのような展望を描いていますか?
現在は欧州電池規則に対応する形でバッテリーパスポートを開発していますが、その対応にとどまらず、事業としてより大きく展開したいです。
バッテリーの次は他の自動車部品へ、さらに非自動車領域へ。今後は欧州で義務化される「デジタルプロダクトパスポート」や、児童労働など人権侵害リスクの調査・予防を行う「人権デューデリジェンス」の領域まで広げ、循環型社会に貢献できる価値を提供したいと考えています。
バッテリー専用のシステム開発でしたらハードルは下がりますが、他の領域にも適用できる汎用的な開発は非常に難しいものです。技術員たちは今、5年、10年先を見据えて開発しており、私も共に取り組む中でスケールの大きさを実感しています。目先だけにとらわれず、未来をイメージして行動することを忘れないようにしたいです。
──菊池さんの「これから」についてもぜひ聞かせてください。
当面はブロックチェーンの量産化開発に注力する予定です。品質第一というデンソーの考えを大切にしつつ、「世に出す緊張感」を肌で感じながら進めていきます。一人ひとりが楽しみながら挑戦し、仲間と共に到達し、達成感を共有できれば何よりうれしいです。
中長期的には「新たな価値を創出し続けられるチーム」へ成長していきたいですね。私自身、技術員の部屋に入り込み、積極的に輪に加わることで視野を広げることができました。後に続く人たちにも、技術員と肩を並べて活動し、得たノウハウや成果をチームに還元できるようサポートしていきたいです。

※ 記載内容は2025年8月時点のものです
COMMENT
「できてない」 を 「できる」に。
知と人が集まる場所。