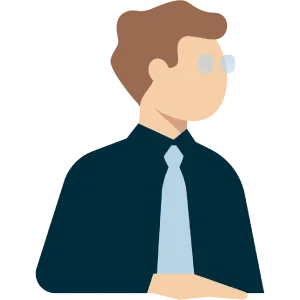あなたが実現したいこと、学びたいこと、可能性を広げたいことに、この記事は役に立ちましたか?
ぜひ感じたことを編集部とシェアしてください。
私たちの便利な生活を支える「物流」は、「2024年問題」と呼ばれる危機に直面しており、物流網全体を最適にコーディネートすることが求められています。
デンソーは、この問題を解決するために、幹線中継輸送に注目したソリューションとして「SLOC(Shuttle Line Of Communication)」を開発。その内容について、2022年にDRIVEN BASEでも紹介しました。
今回は、24年4月に実施したSLOCの実証実験の様子をレポートします。
この記事の目次
幹線中継輸送でドライバーの負担を減らす
幹線中継輸送サービス「SLOC」は、「新しい物流のかたち」 を生み出すためのプロジェクトとして始まりました。
一つの行程に中継地点を設け、複数のドライバーで交代しながら輸送する「SLOC」という仕組みが実現すれば、ドライバー一人当たりの拘束時間が短縮されるとともに、荷主は労働環境を守りつつ、荷物を目的地に運ぶことが可能になると期待されています。
「SLOC」では、荷物を積載する荷台部分が脱着できるスワップボディコンテナ車両を活用。デンソーが開発したQRコード技術を応用した運行管理システムを導入することで、複数の荷主と複数の運送業者を最適に組み合わせて効率的に荷物を運ぶ、新しい輸送形態の実現を目指しています。
以前、DRIVEN BASEで「SLOC」を紹介したのは、本格的な実証実験を始める少し前の時期でした。その後デンソーは、さまざまな業種の会社の協力を得ながら複数回の実証実験を実施。その実証はどのような様子だったのでしょうか。
現地レポート!「SLOC」はいかにして物流を効率化するのか
2024年4月の実証実験では、パートナーとして三井倉庫ロジスティクス株式会社と共同で実施。「SLOC」を導入することで、ドライバーの必要人員数やCO₂排出量の低減につながるかどうかを検証しました。

今回は、中継地点ゲートウェイとなる三井倉庫ロジスティクス名古屋事業所にお伺いしました。トラックドライバーがSLOCを活用してどのような作業を行っているのか、写真とともにレポートしていきます。

関西エリアから荷物を運んできたトラックが中継地点の名古屋に到着し、所定の位置に駐車します。

先述のように、SLOCは荷台(コンテナ)とそれを載せる車台(車両)を分離できる 「スワップボディコンテナ車両」 を使用しています。写真の右側は次のトラックに渡すためにコンテナが置かれています。左側の車両に関しても、同じように車両とコンテナを切り離していきます。

切り離し作業は、コンテナに付属している黄色の脚を下ろすところから始まります。

脚は合計6本あり、5分程度でスムーズに作業を進めていました。

すべての脚を組み立てた後は、車両側の台をゆっくりと下げていき、コンテナと車両を切り離します。最終的には、コンテナの周囲をまわりながら、正しく分離できたかどうかを人の目で入念にチェックし、切り離し作業を完了します。

最後に、「SLOC」の運行管理システムに「到着完了」の登録を行います。

登録作業はとてもシンプル。コンテナ側面に張り出された「QRコード」を読み取ることで、電子機器に慣れていないドライバーさんでも簡単に登録を行えます。
中継地点でのドライバーさんの作業はこれで終了。通常であれば、数十分から数時間かかる荷卸し作業ですが、SLOCの場合であれば10分足らずで帰路につくことを可能にします。

いざ帰路へ。まっすぐ前進しながら、スワップボディコンテナからトラックの荷台をゆっくり抜いていきます。

すぐ近くの自社の名古屋営業所に向けて、ドライバーさんは帰っていきました。

分離したコンテナは、三井倉庫ロジスティクスの名古屋事務所の作業員によって一部の荷物の積卸しを行い、関東エリアに向けて運ぶための別トラックが輸送を引き継ぎ出発します。
今回の実証実験について、現場で立ち合いを行っていた社会イノベーション事業開発統括部の関 正人は次のように語ります

今回は、1台のトラックで多くの荷物を運ぶために、三井倉庫ロジスティクス名古屋営業所を含む複数の中継地で荷物を混載して運ぶ「混載輸送」の実証実験を行いました。1台のトラックで多くの荷物が運べるようになると必要となるドライバーの削減や CO₂の削減に寄与します。
これまでの実証実験においては中継地ではコンテナを入れ替えるだけでしたが、今回、追加で、コンテナ内の荷物の一部の積卸し・積替えを行うことで、複雑な輸送ニーズに応えながら、効率的な輸送に貢献しました。
これらの作業をムリ、ムダなく行うためには、三井倉庫ロジスティクスの現場の理解とモノと情報の連携が不可欠となります。我々は、先方の現場に入り込み、一体となって連携しながら、「SLOC」の最適なかたちを模索し、社会実装に向けて挑戦しています。
実証実験を経て、2025年の事業化へ
これまでの全6回にわたる実証実験を経て、「SLOC」はドライバー数やCO₂排出量の低減に貢献できることが確認できました。現在、2025年の事業化を目指してさらなる改善を進めているフェーズにあります。
次回の記事では、SLOCの事業化を推進するメンバーへのインタビューを通じて、今後の展望をお伝えします。
COMMENT
SHARE
「できてない」 を 「できる」に。
知と人が集まる場所。