
サステナビリティマネジメント
デンソーにとってのサステナビリティ経営
サステナビリティ経営とは、社会のサステナビリティの視点を経営戦略に採り入れることで、当社の企業価値向上を図っていくこと、つまり「事業を通じて社会課題解決に貢献すること」です。
デンソーの社是にも「最善の品質とサービスを以って社会に奉仕す」とあるように、同様の精神が記されており、創業以来、脈々と受け継いできた当社経営の根幹であり、成長の原動力です。
サステナビリティ経営の歩み
クルマは元来、安全で快適な移動という正の側面と、排出ガスや交通事故などの負の影響を併せ持っています。デンソーは創業以来、どんなときでもクルマの正の最大化と負の最小化という社会課題と真摯に向き合い、より環境にやさしく安全で快適便利なクルマに貢献しつづけたことで成長してきました。
創業時の経営難時代に電気自動車「デンソー号」(1950年)を作ったのも、その志の表れです。1970年代からは、世界中の拠点で、モノづくりとヒトづくりを通じて雇用創出と地域社会の発展へも貢献してきてきました。
また、クルマで培った技術をFAや農業分野にも拡大し、労働力不足や食料不足という新たな社会課題にも取り組んでいます。
このように、デンソーは、いつの時代も事業と社会課題解決を両立させるサステナビリティ経営を実践してきており、これがデンソーのDNAと考えています。
サステナビリティポリシー
デンソーグループの社員一人ひとりが、社会やステークホルダーとのつながりの中において、社是やデンソー基本理念に沿ったグローバル企業としてふさわしい行動を実践できるように「デンソーグループサステナビリティ方針」を定めました。行動宣言へのコミットメントとして、代表取締役社長、全国内外グループ会社社長が署名しています。
マテリアリティ
デンソーは2006年度にデンソーグループ企業行動宣言(デンソーグループサステナビリティ方針の前身)を制定した際に、重点分野を設定して以降、社会動向やステークホルダーの期待を踏まえて都度マテリアリティの見直しを実施しています。
現在のマテリアリティは、社会に存在する様々な課題の中から、社会にとっての重要度・会社にとっての重要度、ならびに、「デンソーグループ2030長期方針」において宣言した3つの領域「環境」「安心」「共感」を踏まえて、2018年度に設定しました。マテリアリティに対して、それぞれKPIを設定し、会社目標として経営審議会、取締役会にてフォロー、審議しています。また、このKPIの一部を役員報酬の算定指標に組み込み、2022年度から運用を開始しました。
環境変化を踏まえたマテリアリティの見直し
社会課題や事業を取り巻く事業環境の変化を踏まえ、デンソーでは、2018年に設定したマテリアリティのアップデートを行っています。国際社会やステークホルダーからの関心の高い社会課題を網羅的に抽出した上、“デンソーの事業活動が社会に与える影響”、“デンソーにおける重要性”の両観点から機会・リスクを洗い出し、時間軸も考慮に入れて定量的に評価を実施しました。
マテリアリティ案については、顧客・取引先・投資家・社員・地域といったバリューチェーンを代表する主なステークホルダーとの対話を通じていただいた意見やデンソーへの期待を反映、最終化しました。その後、経営レベルでの議論を経て、取締役会にて承認されています。現在、次期中期経営計画の前提としてマテリアリティを据えて目標を設定し、各部門・地域の活動計画を策定中です。
今後はサステナビリティを取り巻く状況の変化を踏まえて毎年マテリアリティを見直すとともに、年に2回、サステナビリティ会議にて各マテリアリティ達成に向けた活動進捗の確認を行っています。
マテリアリティの見直しプロセス
|
網羅性の確保 |
社会課題の抽出 |
|---|---|
|
デンソーらしさの反映 |
自社重要戦略・課題の抽出 |
|
評価 |
定量評価の実施 |
|
社会からの期待を確認 |
社内外ステークホルダーとの対話 |
|
最終化 |
経営レベルでの議論・承認 |
社内外ステークホルダーとの対話
|
顧客 サプライチェーン全体での人権尊重の重要性が増してきており、事業リスクとなりつつある。取引先様へも活動強化を要請する予定のため、デンソーにおいても優先順位を上げてリスクの最小化に向けた活動をしてほしい。 |
|
|
サプライヤー デンソーのマテリアリティについて、中小企業が同じレベルで活動できるわけではないので、サプライヤーとともに進めるテーマの優先順位をつけてほしい。また、企業単独ではできないテーマも多いため、デンソーからの継続的なサポートを期待。 |
|
|
機関投資家 選定したテーマは納得性がある。今後はマテリアリティが企業価値向上にどのように結びつくのか、や、中長期の目標を明確にして発信してほしい。 |
全社リスクとしての管理
特定したマテリアリティのうち、当該リスクの発生頻度や影響度を踏まえて、環境(特に気候変動)・情報セキュリティ・労働安全などについては、リスクマネジメント会議が特にリソーセスを投入して対策を推進する「重点リスク」に選定されており、全社リスク管理の観点からもグループ全体でリスク対応を強化しています。
推進体制
経営戦略本部を担当する役員を統括責任者として、経営戦略部が全社のサステナビリティ経営推進機能を担っており、デンソーグループのサステナビリティ経営の方向付けを全社視点で議論する場として、サステナビリティ会議を設置しています。サステナビリティ会議は、機会とリスクの特定や、策定したマテリアリティ案の審議及び活動のフォローアップと軌道修正を行うなど、サステナビリティ経営の推進に責任を持っており、議論内容については取締役会に付議・報告をします。
なお、サステナビリティ経営の推進の重要な担い手である社員一人ひとりの意識を醸成するため、個人の年度目標設定の際に、自身の仕事と社会課題解決とのつながりを見える化するなどしています。
また、職場におけるサステナビリティ浸透の牽引役として、(株)デンソーでは各部門1名、国内グループ会社は各社1名、海外グループは各地域統括会社から1名のサステナビリティリーダーを選任し、サステナビリティの浸透・定着・情報発信を図っています。
サステナビリティ体制図
| 議長 | 取締役副社長 |
|---|---|
| 構成 | 各マテリアリティ推進責任者(役員クラス) ※事業や地域で連携すべき議題の際には各事業G長、地域長も出席 |
| 目的 |
|
| 開催頻度 | 2回/年 |
具体的な活動 ~サステナビリティの社内浸透~
全部門・全社員が日頃から、仕事を通してどのように社会課題の解決に貢献していくのかを考え、行動することがサステナビリティ経営の実践であり、社会課題を解決していくための第一歩になると考えています。
そこで、社員一人ひとりが自分の言葉でサステナビリティ経営について語り、行動できるように、デンソーグループの各地域・各社でそれぞれの文化・風土を踏まえた効果的な社員啓発や情報発信などの施策を考えて活動しています。
なお、社員を含めたステークホルダーが、デンソーの取り組みを社会とのつながりで理解しやすいように、国際共通言語となったSDGsを活用し、情報発信やコミュニケーションを図っています。
-

キャラバン(EU)
-

社内報(日本/京三電機)
-

e-ラーニング[アジア]
-

ワークショップ(中国)
【Topics】私のSDGs取り組み [(株)デンソー]
-
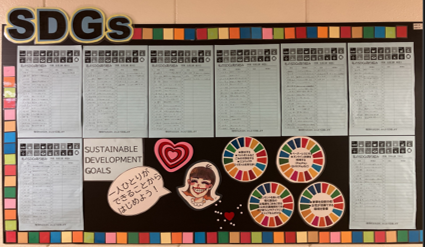
-
幸田製作所では、「キラッ人キャラバン※」などを通じ、各職場単位でサステナビリティ経営を理解できるように促してきました。同製作所のセミコンダクタ製造部では、「私のSDGs取り組み」と題して、社員一人ひとりが自分の業務や行動を通じてどのように社会のサステナビリティに貢献したいか、350名を超えるメンバーが参加し、その目標を書き出して、製作所内で掲示しています。自分の行動を振り返るとともに、職場の仲間の宣言を知ることにより、新たな気づきを得るきっかけとなっています。
※各部門長、工場長、各部サステナビリティリーダーによるSDGsワンアクションの事例紹介をする取組み
(株)デンソーの取り組み
社員啓発
サステナビリティを多角的な視点から捉え、仕事と社会課題とのつながりを理解し行動を促すため、社外講師(投資家・企業のサステナビリティ担当役員・国際機関)による講演会や社員間で理解を深めるワークショップを開催しました。
-

講演会
年度計画におけるサステナビリティの見える化
全部門・全社員がサステナビリティの理解を深めるため、年度計画を策定する際、各部門では組織の役割と年度の重点取り組みテーマについて、各社員は業務の個人目標について、社会課題解決とのつながりをSDGsを活用し、計画を策定しています。
【topics】従業員証へのSDGsの表示 [(株)デンソー、アジア、韓国]
-
年間の個人業務目標を設定するにあたり、自分の業務がどのSDGs目標に貢献するのかを考えるとともに、その目標を従業員証や名刺などに表示しています。それにより、自分自身が設定したSDGs目標をいつでも振り返ることができ、さらには周りの仲間にも共有することで、折に触れてSDGsへの貢献について語るきっかけとしています。
-

情報発信
統合報告書や会社webサイト、ニュースリリースなどの発行による社外発信だけでなく、社員一人ひとりがお客様や家族などのステークホルダーに積極的にサステナビリティについて語ることで社会へ発信することを目指しています。
そのためには、社員それぞれがサステナビリティ事業戦略を正しく理解することが重要です。
トップによる環境・安心戦略の紹介を動画等にて社内イントラネットに掲載し、社員の理解を深める取り組みをしています。
社員浸透状況の把握
社員のサステナビリティに対する理解・実践度合いを把握・点検するために、意識調査を実施しています。
【事例紹介】 サステナビリティサーベイ
社員のサステナビリティに対する理解・実践度合いを把握・点検するために2006年から毎年実施しています。
2024年度調査結果(回答数約1,700人)
質問①:自分の仕事がどのようにSDGsに貢献しているか理解していますか?
(株)デンソーでは2019年度から、自分の仕事とSDGsのつながりを理解するため、個人の年度目標設定の際に、どのSDGsに貢献するのかを明確化する施策を実施してきました。回数を重ねるにつれ、面談などでの上司との議論の時間が減少していると考えられます。今後は会社の優先取組課題である“マテリアリティ”をメインに据えた浸透活動を推進していき、社員一人ひとりが“自分の仕事とマテリアリティのつながり”を理解することを目指します。
質問②:サステナビリティ/SDGsに対するあなたの考えに近いものを選択(複数回答)
社会との対話

ステークホルダーとの対話
自社の論理や思いこみにとらわれて独善的な活動とならないように、ステークホルダーの皆様との対話を大切にしています。































