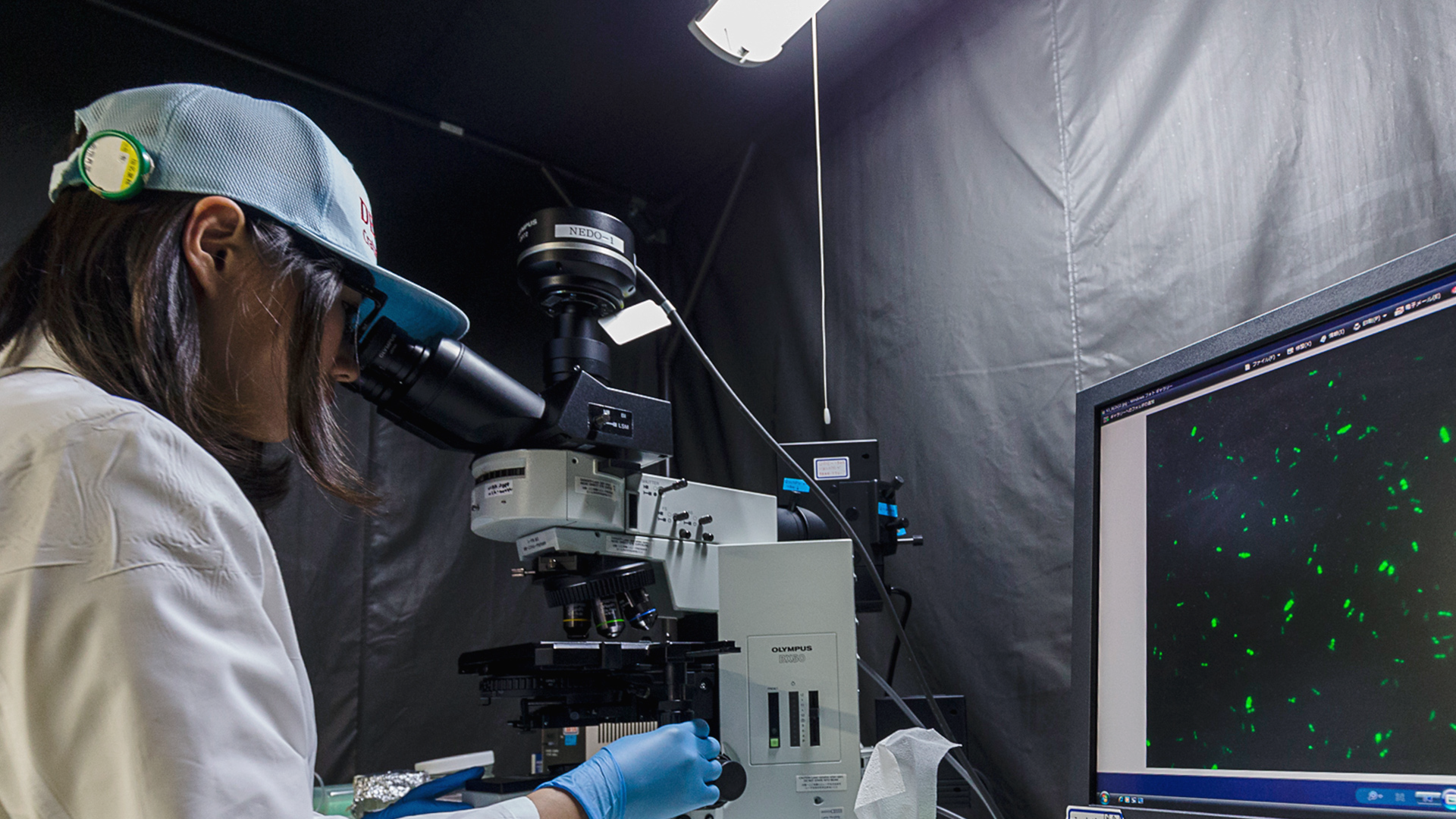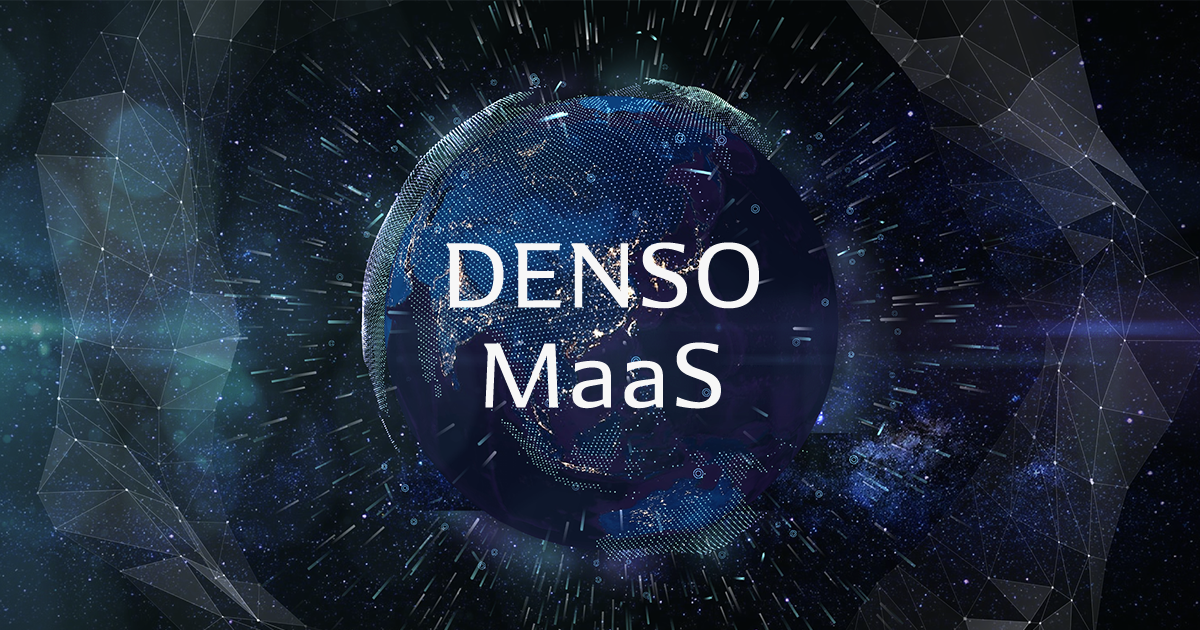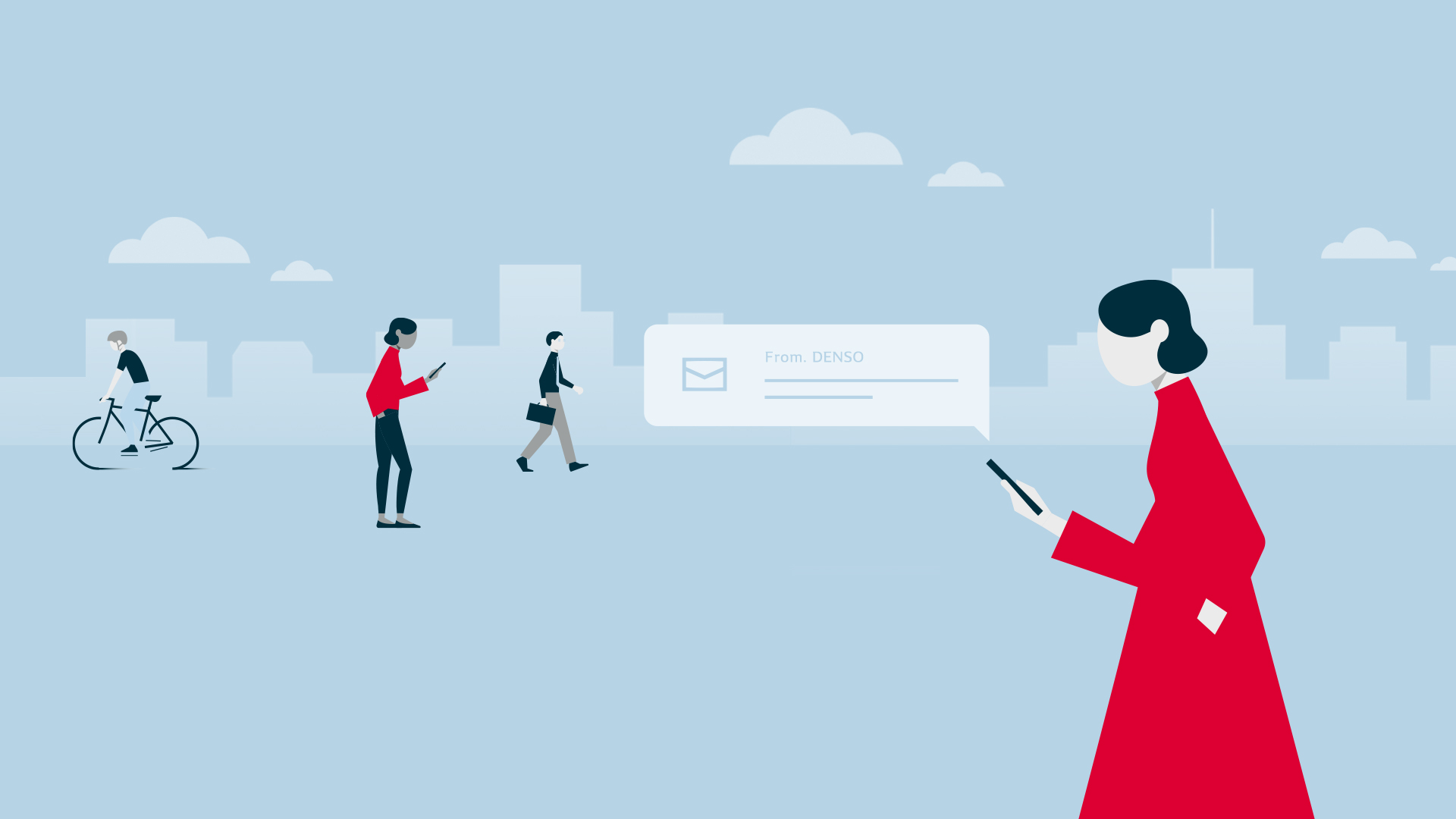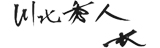外部からの評価
第三者意見
IIHOE※【人と組織と地球のための国際研究所】
代表者 兼 ソシオ・マネジメント編集発行人
川北秀人 氏
※IIHOE:「地球上のすべての生命にとって、民主的で調和的な発展のために」を目的に1994年に設立されたNPO。
主な活動は市民団体・社会事業家のマネジメント支援だが、大手企業のCSR支援も多く手がける。
https://blog.canpan.info/iihoe/
デンソーグループのサステナビリティ/CSRへの取り組みに対する第三者意見(2022年度)
当意見は、デンソーグループのウェブサイト上のサステナビリティ/CSR関連ページの記述内容、および同社の環境、調達、品質・顧客満足、人事、健康推進、安全衛生、総務(社会貢献)、サステナビリティマネジメントの各担当者へのヒアリングに基づき、23年12月末時点までの取り組みについて執筆しています。
同社のサステナビリティ/CSRへの取り組みは、「デンソーグループ サステナビリティ方針」に基づき、その広範な項目に数値目標を設け、進捗や課題を定量的に管理するマネジメント・サイクルを国内外に展開しており、世界的にベンチマークされるべき水準を維持していると言えます。今後も、環境・安心・共感の3つの課題への取り組みを進める上で、品質や安心に対する信頼を適切に再構築するために、市民との対話や市民への開示を拡充し、共感を向上することが、強く期待されます。
高く評価すべき点
-
サステナビリティ/CSRマネジメントについて、「デンソーグループ2030年長期方針」において、環境負荷の低減と高効率な移動による持続可能な社会づくり、交通事故のない安全な社会と快適で自由な移動によるすべての人が安心して暮らせる社会づくりを、社会から共感される新しい価値づくりを通じて実現することを宣言していること、その主要項目についてKPIを設定し、各部門・担当において多様かつ実務的な社会責任への取り組みを、リスクマネジメントとステークホルダー満足の2つの観点から網羅的かつ定量的に管理しながら進めていることを、高く評価します。一方で、その方針策定や経過の評価などに関する社外のステークホルダー、特に市民との対話やエンゲージメントについて、より早く・より高い段階で、より広範かつより深く行われること、具体的には、長期方針の策定や進捗の共有を市民とともにする機会の設定を、引き続き強く期待します。
-
持続可能な調達について、取引先におけるサステナビリティ/CSRマネジメントの基盤づくりのために、安全・品質、人権・労働、環境、コンプライアンス、情報開示、リスクマネジメント、責任ある資源・原材料調達、社会貢献、サプライヤーの取引先への展開の9項目に関する「サプライヤーサステナビリティガイドライン」と「同 自己診断シート」をウェブサイトで公開し、国内外のグループ会社の一次仕入先に対しては、同ガイドライン遵守に向けた手引きの配布、自己診断シートによる自己診断とフィードバックを終えて改善を働きかけていること。特に、小規模事業者における環境マネジメント体制を確認するツールを独自に策定することで、グループ内はもとより、主要な取引先においてもサステナビリティ/CSRが現場の日常のマネジメントに落とし込まれるよう促していること、世界最高水準と言える自社内の取り組みをサプライヤーに紹介し、その推進ツールを貸し出していること、さらに、サプライヤーのカーボンニュートラル実現を促進する専任部署を設けることは、世界的にもベンチマークされるべき水準であることを、重ねて高く評価します。また、21年度に続いて、日本国内の430社について、外国人技能実習生の受け入れ状況等に関する実態把握を行ったこと。今後は、さらに特定技能資格の拡充により外国人が基本的な権利を認められより長期に働けるようになることから、より長く働き続けてもらえるサプライヤーが増えるよう、改善を促すべき対象への具体的かつ効果的な働きかけを、引き続き期待します。
-
環境経営について、2035年を目標年とするモノづくりの完全なカーボンニュートラル達成を宣言し、着実に実現しつつあること、また、社内炭素価格を設定し、事業ポートフォリオや投資判断の基礎としていること。安城製作所などでCO2循環プラントの実証実験を続けていること、国内外の製造所において再生可能エネルギー調達を順次進めていること。今後は、ユーザーの使用段階における環境負荷の低減について、完成品メーカーと連携して取り組みを進めることを、引き続き強く期待します。
実践面において、既に世界最高水準にある製品・生産両面の環境効率や資源生産性をさらに追求するために、各部門・担当において詳細な項目に定量目標と推進計画を設けて、全社横断的に展開し検証していること。その基盤となる「ボトムアップで現場主導の取り組みを促す風土」と「やると決めたらやりきる文化」において同社は世界的に傑出し、サステナビリティへの貢献や社会責任への取り組みの進化の源泉であると言えます。「パーフェクトエネルギー工場(PEF)活動」の世界展開や、生産部門と施設管理部門が「エネカンバン」により電力、ガス、圧縮エア、空調、蒸気、水や照明まですべての資源の需要情報を予め共有し供給を最小・最適化する「エネJIT」(エネルギーのジャスト・イン・タイム)を通じて、現場が自ら改善のポイントに気付くしくみづくりは、世界中の製造業からベンチマークされるべきベストプラクティスであり、その全社展開が省エネルギー大賞を受賞したことは、当然の評価と言えます。
また、16年度に発表された「エコビジョン2025」において、エネルギー1/2(のちにニュートラルに改訂)、クリーン2倍、グリーン2倍のターゲット3と、それを実現するアクション10を明示して着実に推進していること。特に、エネルギーのマネジメントを、全社・生産・供給それぞれで最適化するシステムを確立していることに加えて、カーボンニュートラル工場ロードマップを策定していること。水について与える・被るリスクと貢献する機会の側面から、リスクマネジメントを実践していること。今後は、サービス・ステーションなど世界全体のヴァリューチェーン全体を視野に入れ、海洋生態系や生物多様性への影響が指摘されるプラスティックの使用・リサイクル状況の把握や改善、自社や取引先などが集積する地域の水源林や下流の水域等における生物多様性保全に拡大的に取り組むなど、ターゲット3がより広く深く達成されること、リビルド製品の利用促進や、信号システムや充電ポイントなどの社会インフラストラクチャと連携した燃費の改善、また、軽量化や高効率化を加速するための機能性樹脂をはじめとする素材の開発にも、強く期待します。 -
社員の健康について、課長級を健康リーダーに任命し、職場単位の年間計画の策定と実践を求めるとともに、個々人の生活習慣の実践状況を健康診断データから点数化した「生活習慣スコア」を全社目標としていること、特に個々人の生活習慣について食事・運動・飲酒・睡眠・喫煙という「行動」とBMIなどの「健診結果データ」から定量的に把握し、個人と職場に改善を具体的に促し、特定保健指導の教育開始が96%に達し、また、支援の早期化により対象となった30歳代の9割近くが2kg以上の減量を実現していること。今後は、増加しつつあるメンタル疾患への対応や予防として、現在実践されている高リスク職場への個別支援や相談の促し、ストレス対処力向上に関する研修に加えて、当事者やその同僚・上司などの経験の共有、さらに、他者との協働の機会が少ない世代に適した育成手法の開発にも、期待します。
-
職場の安全づくりについて、従来の防火管理自己点検シートに加えて、当方の提案に基づき、損害保険会社による診断・助言も活用していること。今後は、取引先においても「人と施設・設備の高齢化」が進むことから、資格制度を活用するなど人材育成を促すとともに、アプリなど安全や健康への取り組みの基盤となる管理体制の支援ツールの開発・普及に、引き続き期待します。
取り組みの進捗を評価しつつ、さらなる努力を求めたい点
-
コーポレート・ガバナンスについて、コーポレートガバナンス・コードを踏まえた社内役員制度の変更を含めた体制の整備・実践ならびに情報の開示を進めていること、さらに15年6月制定の「基本方針」に「株主以外のステークホルダーとの適切な協働」を明記していることを評価しつつ、今後は、取締役を含む経営層における価値・文化的な多様性を向上しつつ、特に取締役については従業員・他の役員とのシナジーが生まれる構成となるよう配慮すること、また、マテリアリティ策定を含む同社の重要な意思決定に先立って、世界の主要な地域において対話の機会が拡充されることに、引き続き強く期待します。
-
安心向上のための交通事故ゼロに向けた取り組みについて、GSP3の開発により、事故場面の7割までカバーされるとともに、ペダル踏み間違い加速抑制が開発されていることなどを評価しつつ、自動・自働は重要ではあるものの、モビリティの主体である人や社会の参画が不可欠であることから、エンゲージメントの機会を積極的に設けることを強く期待します。
-
顧客満足の向上について、製品の修理によるCO2削減量やその背景を詳しく明示していること。今後は、環境負荷削減とサーキュラーエコノミー2つの側面において、最も重要なパートナーである顧客の実践を促し支援するために、整備・解体事業者などを中古品調達先と位置付けるビジネスモデルの開発をはじめとするしくみの整備や、他社と共有し得るプラットフォームの形成に、強く期待します。
-
国際・地域社会への貢献活動について、環境・安全安心・人づくりを重点分野と位置付け、約8,000人の社員が参加する「はあとふる基金」、アジア車いす交流センター(WAFCA)などによる障がい者支援ならびに障がい者スポーツ支援、サイエンススクールの開催、本業を生かした大規模被災地の復興支援の実践と体制整備、交通安全啓発をはじめとする多様かつ先駆的な取り組みを評価しつつ、今後は、事業活動と社会課題解決との統合的な実践、一例として、世界のグループ従業員全員が「交通安全指導員」としてコミュニティで活躍し、地域交通安全マップや人材育成カリキュラムの作成など自社のサービスや強みを最大限に発揮するとともに、交通事故ゼロに向けた社会の基盤づくりなどが進められることを、引き続き強く期待します。
グローバル企業として、取り組みの進展が期待される点
-
長期方針を実現する価値創造プロセスについて、目指す姿として掲げられた「地球にやさしく、すべての人が安心と幸せを感じられるモビリティ社会」を、社会と自社の持続可能な成長の成果として実現するために、2030年代の国内外の人口構成や、気候変動対応をはじめとする社会経済状況を見通して、インフラストラクチャー(社会基盤)やクルマがどうあるべきか、特に、日本をはじめ各国で急増する高齢者の近距離・低速移動(アクセシビリティの保障)と、化石燃料を使わないモビリティの実現に向けて、積極的に提案する姿勢を、引き続き求めます。
-
人権への取り組みについて、調達部門による調達先の体制や実践の把握ならびに改善の働きかけが進められていること、人権方針が策定されたこと、人権リスクアセスメントに着手したことを評価しつつ、グループ内、およびヴァリューチェーンの下流プロセス(特にリサイクル工程)における取り組みの改善を促すために、ヴァリューチェーン全体での人権マネジメント体制(具体的にはトップマネジメントの具体的なコミットメント、デューディリジェンスの実践と救済体制)が整備されること、特に日本国内においては、外国人の技能実習制度の大幅な是正を機に、グループのみならず取引先においても長期に働き続けたいと感じられる職場づくりの促進を、引き続き強く期待します。
-
社員尊重と人的多様性について、障がい者雇用において先駆的な取り組みが積み重ねられてきたこと、日本国内の女性管理職比率向上のために採用・両立・昇格の均衡について取り組みを進めていることを評価しつつ、男女の勤続年数差が残っていることから、今後も引き続き、子育ても介護も看護も、家族を支えながら仕事し続ける職場環境・制度の整備を進め、会議など意思決定や業務の在り方について定量的に見直しが進められることを期待します。また、海外拠点長に占める現地人材比率向上の取り組みが進められていることを評価しつつ、2030年代以降を見据えて、事業実現力と量産実現力の基盤として、社内外の「人々の力を生かす力」が育つ機会を設けるとともに、世界各地で働くより多くの従業員が、自らの母語でデンソーの理念・価値観や実践を理解できるよう、上級管理職候補者層の交流や通達・広報物の多言語化がさらに進むことに引き続き強く期待します。
-
取り組み紹介の深さとタイミングについて、情報開示については方針が定められているものの、環境や社会など広範な項目への取り組みの紹介について、より深く、より適時に行うために、また、未来に同社が担うべき機能や社会に生み出すべき価値などについて、市民との対話の機会をより多く深く設けることを、引き続き強く期待します。